僕はヴェネツィアに行ったことがない。
けれど僕の中にはヴェネツィアの、空間、時間、温度、湿気、喧噪、静寂のイメージが棲
んでいる。そいつはねっとりと、身体の奥底に溜まって離れようとしない。まるで夜のヴ
ェネツィアの細い水路の翳りの中で鈍く光る、黒い水のように。
それは、この本に出会ったからだ。
ヨシフ・ブロツキー作「WATERMARK(邦題 ヴェネツィア・水の迷宮の夢)」。
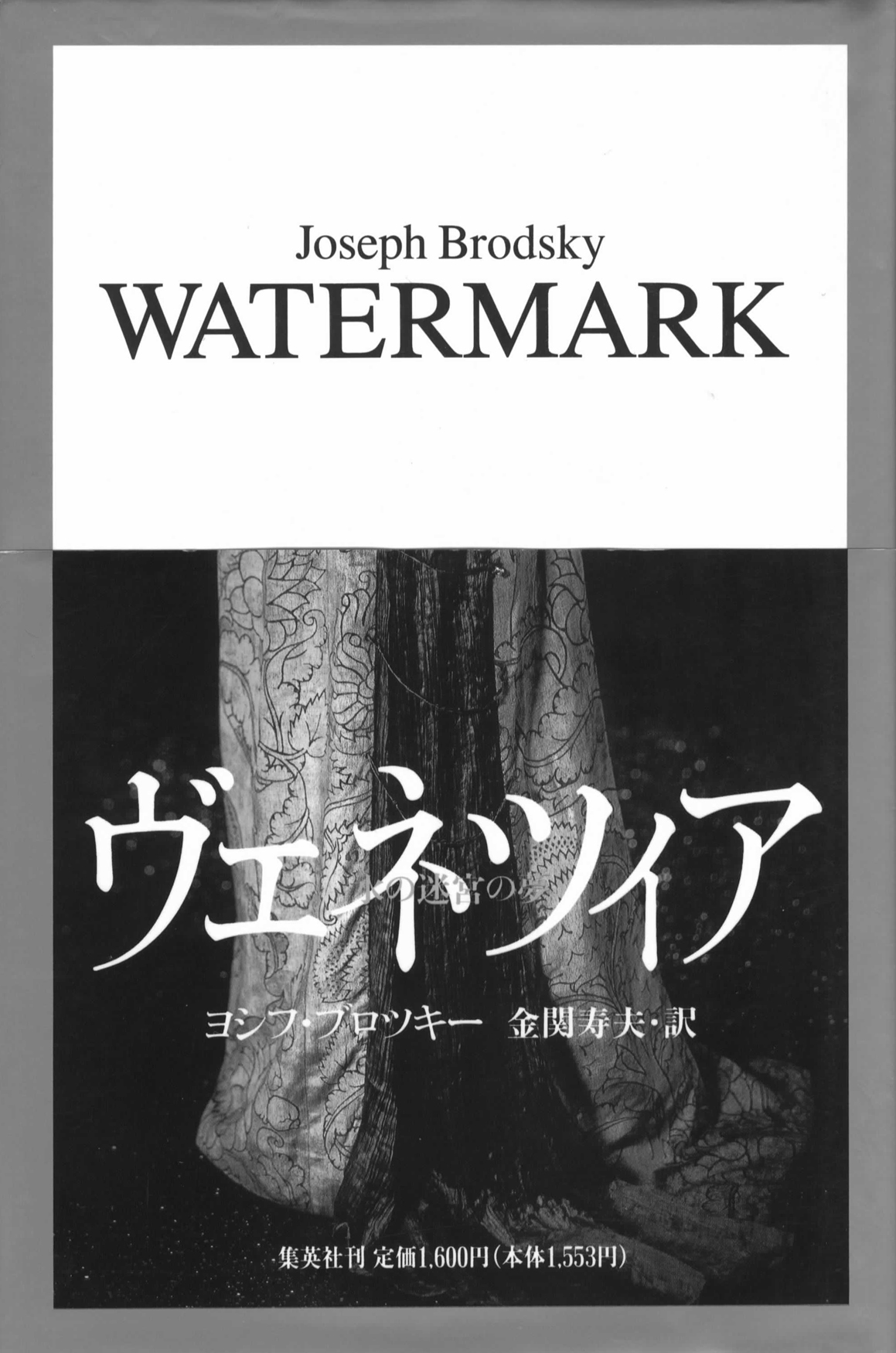
ブロツキーは1940年生まれのロシアの詩人である。
ソヴィエト連邦と呼ばれていた当時の彼の国では、詩人というのは「有益な仕事に就こう
としない徒食者」として迫害の対象とされたらしい。実際、1963年に彼は逮捕され、
強制労働の判決を受けた。そして1972年には国外追放。両親とさえ永遠の離別を余儀
なくされる。
ロシア語を愛し、言語の純粋性を追求する文化的な創作が、当局にとっては「有益な仕事
」ではないという。その極端な価値観と、抗えない強制力には戦慄を覚えるが、ともかく
もブロツキーはアメリカへ渡り、自由な活動の場を得た。大学で詩を教えながら創作を続
け、1987年にはノーベル文学賞を受けている。
「WATERMARK」はその2年後、1989年に英語で執筆された散文の作品であり、1
992年に発行。日本でも1996年に金関寿夫氏の訳で出版された。
日本語版に付されている高橋雄一郎氏の<解説>には以下のようにある。
「___ヴェネツィアの水と光をモチーフに、多くの隠喩やアフォリズムを織り込んだフ
ーガのような作品である。また語り手の主体が意図的に曖昧にされ、全体がある虚構性に
包み込まれている___(<解説>より抜粋)」
ヴェネツィア。ブロツキーにとってその街はどんな場所/存在だったのだろうか。
アメリカに亡命以来17年間、毎年冬になると詩人はその街を訪れた。イタリアといえど
も冬のヴェネツィアは寒く、しかし、それが彼を癒した。
人間の嗅覚と記憶との興味深い関係はここで記すまでもないが、この街で最初に辿り着い
た駅舎の階段で唐突に出会った「凍った藻の匂い」は、彼が子供時代を過ごしたバルト海
を、あるいは遥か彼方、人間が脊索動物だった頃の記憶の蓄積を想起させ、彼を個人的な
幸福に導いたという。
ブロツキーが追放されたソヴィエトを前世と呼ぶとき、ダンテの「神曲」に準えて、現世
であるアメリカを煉獄、そしてこの街を天国とも呼ぶ。
彼の人生の前半に、ヴェネツィアとの繋がりを予告する他愛もない幾つかのことがあった
として、実際のところ最初の渡航の目的のおそらく半分は、たった一人の知り合いの(息
を呑むほどに美しい)ヴェネツィア女性だった。しかし詩人はヴェネツィアそのものに魅
入られてしまうのである。「天国の概念は、純粋に視覚的なもの」と信じる彼故に、その
水上都市の視覚的な魔力によって。
魔力の媒体は、すなわち「水」である。
辞書によると原題の「WATERMARK」の第一義は、(港や河口で潮の高さを示すために
取付けられる)「水位標」のことだ。しかし上記の<解説>でも触れられているように、
その単語の響きは同時に水面の波紋や、水のつくるシミ、さらに水によって刻まれる刻印
などをも連想させる。
この本を読んでいると、水面を鏡として浮かんでは消える映像、明滅する光と影のイメー
ジに度々出会うが、その一方で、千年の時を越えて運河に足元を洗われ続けるパラッツォ
の基壇に刻まれた縞模様に言が及ぶのを見つけることも出来る。この刻印は「時間」と同
義だ。
つまりこれらは、瞬間と永遠を同時に見せるのだ。
英語で書かれた原文を読んでいないので推測に過ぎないが、詩人の記した散文のこと、韻
を踏んでいるということがかなりあるのだろう。高度な韻律は音遊びを超えて連想を呼び、
テクストの下に潜む別のテクストを見せたり隠したりする。
実際「ロシア語の発想を使って、英語の読者には分からない意味を作品の下地に塗り込め
てしまう、騙し絵のような洒落を得意とするらしい」ブロツキーのテクストは、それ自体
が細波立つ水面の様だ。乱反射を丁寧に取り除くと、その深みには別の意味が浸されてい
るのが見えてくるのかもしれない。それこそ「WATERMARK」の第ニ義である「透かし
模様」のように。
きっと、詩人が「WATERMARK」という言葉に仕込んだイメージの連鎖も、瞬間と永遠
を同時に見せる水を媒体として、魔法のように広がっていくのである。
こう考えると、日本のマーケット対策とはいえ、邦題「ヴェネツィア」というタイトルに
わざわざ付された「水の迷宮の夢」という副題がいかに説明的に過ぎて無粋かが知れてし
まうけれど。
++
話は少し逸れてしまうが、この本に出会った1996年のさらに十数年前、子供だった僕
には繰り返し夢想していた一つの映像があった。魚が空を泳ぎ、鳥が水中を飛びかうイメ
ージだ。
トビウオなら空を飛ぶし、ペンギンだって海を泳ぐだろう、という話とはちょっと違う。
僕は地面にしゃがんで水溜まりの中を覗き込み、無数の小さな生き物が漂う様を観察しな
がら何時間でも呆けている子供だったけれど、当時の僕にとって、水と空気は密度と比重
が異なるだけのひと連なりの同種の存在で、水と油がつくり出す境界と水と空気との境界
は、全く等価で並列の事象だった。
いま考えれば、水でも空気でもいわゆる流体の中で浮遊するように生きるいのちに、嫉妬
していたのだと思う。「魚が空を、鳥が海を、」というのは、嫉妬の対象である彼らが本
来の属性を離れてさらに自由に生きることに対する憧れの、無意識の映像化だったのかも
知れない。何れにせよ、地球の表面に積層する密度の違う流体に残された自由に対して、
その底に沈殿し凝結した泥土の重さ、そこに足を捕われる人間の不自由さが、何よりもど
かしかったのだ。
そういう意味において僕の中で「水」は、空とそして自由と繋がりながら、決してその中
に入り込むことが出来ない目の前に横たわるもう一つの宇宙だった。
水溜まりを覗き込みながら自分自身も覗かれているように思われて、その水面に映る雲を
見ては何度も自分の後ろの空を振り返る子供は、地球をボールの様に抱える巨人キュクロ
プスの一つ目が雲間から覗いていると信じていた。そして僕が覗く水の中にもまた小さな
水溜まりがあって、その前でしゃがみ込む小さな存在があるはずなのだ。
そう、僕にとっての宇宙は繰り返し積層するものだ。おそらくはマトリョーシカの入れ子
のように。核と電子で構成される原子の姿と、地球と月、太陽系や銀河系の姿が相似形で
あるように。そして、ヴェネツィアを構成する水路がヴェネツィア自身の姿を映し込むよ
うに。
++
いつも水がイメージの投射膜だった。
水といえば同じロシアの映画監督、タルコフスキーを思い出す。彼は映画で詩を紡ぎ、そ
の映像にはいたるところに水が現れる。
「ロシアでは大量の水を、イタリアより遥かに多く見ることが出来る」という彼は、「水
は動きを、深さを、変化や色彩を、反映を伝える。水は地上でもっとも美しいもののひと
つ」だと、あるドキュメンタリーフィルムの中で語っている。
ブロツキーの水とタルコフスキーの水。
同じロシアの感性によって捉えられた「水」なのだけれど、僕は違う印象を持っている。
タルコフスキーにとっての水は、扉のようなものではないか。アチラとコチラを結び、あ
るいは隔てている。現実と虚構を結ぶ媒体として、時には障害として、多様な状況の表出
を仲立ちする。水は海になり、土砂降りになり、水溜まりになり、小川になり、蒸気にな
る。静かなれどもダイナミズムを伝えるものだ。特に蒸気はその曖昧な集合で時間を無効
化する。それが現われつつあるのか消えつつあるのか、物の輪郭を隠すことによって時間
の対極で空間を喚起するのだ。
一方、ブロツキーが描く水は固定されている。固定という言葉が水にとって相応しくない
ならば、コンティヌオ(通奏低音)として常にそこに在る、と言えば良いだろうか。たと
え旋律が、美しい女性や鏡の館のことを奏でているときにでも。きっとこれはヴェネツィ
アで生きる感覚と近いのだろう。日々の生活があり、それと直接関わろうが関わるまいが、
水もそこに在る。彼が「水」と「時間」を同義だと主張することが、別の角度からもそれ
を証明している。
ちなみに、ブロツキーが描写する霧は、水と分離され「乗り込んで来る」ものとして描か
れている。創造力逞しく擬人化されたりして。
++
この本に、話の結末は見つからない。この本の魅力は迷い込むことにあるからだ。ヴェネ
ツィアという迷宮を実際に彷徨うように。方向感覚の喪失は時間感覚をも曖昧にして、あ
る種の浮遊感を生む。いつのまにか僕は子供の頃に憧れた流体を漂う生きものになってい
る。
幸福とは「自分が内部に持っている何かが自由に宙を漂っているのを見つけた瞬間に生ま
れる感情」というのは、ブロツキーの言葉だが、彼がヴェネツィアに通い続けた理由も、
水の迷宮に身を浸して、ただ漂っている時間を求めたからではなかっただろうか。
ヨシフ・ブロツキーはこの本が日本で出版された僅か6日後、1996年1月28日にニ
ューヨークの自宅で死去した。
原著 : Joseph Brodsky
翻訳 : 金関寿夫
価格 : ¥ 1,890 (税込)
単行本 : 151 p
サイズ : 756(hundredths-inches)
出版社 : 集英社






